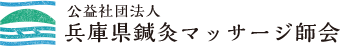2025/03/25
《第11回小野ハーフマラソン2024》
小野ハーフマラソン、鍼灸マッサージ施術ボランティア参加報告
12月8日(日)小野市で第11回小野ハーフマラソンが開催されました。第1回大会からボランティア活動をさせていただいている大会ですが、年々規模も大きくなり、今では参加者が5500人を超える大会となっています。今年の天候は快晴でしたが、最高気温が10度を下回るという12月上旬にしてはとても寒い日となりました。
今年度は初の試みとして、走る前のランナーの方々に声かけをして施術を行いましたところ8名の方が来てくださいました。寒くて体が動かないとか練習中からの痛みに不安を抱えている方がほとんどで、体を動きやすくするように足三里への灸とストレッチを行いました。とても寒い朝でしたので温熱刺激は効果が高く、皆さん「動きやすくなった」とおっしゃってくださいました。問題点としては、当初は皮内鍼をする予定でしたが、昨今のウェアーはきつめのレギンスが多いので足を出す事ができず鍼もテーピングも出来ませんでした。会場に到着してから招集時刻までの時間が少ないので施術の順番を待てないという事もありました。
完走後の方にはマッサージか鍼で施術を行いました。鍼の希望者も増えてきており、初めての方でも施術しているのを見て興味を持ってくれたり、体験していただける良い機会になっていると思います。しかし鍼施術はマッサージよりも時間を要するため、回転率が悪くなり待ち時間の増加につながってしまいます。一人あたり7~8分の限られた時間の中での効果的な施術と、冬のテントの中での鍼施術に配慮した空間作りにはまだまだ課題があると思いました。
今回の受療者は計77名でした。「昨年もお世話になりました」と言われる事も多くなり、昨年良かったからと指名される方までいらっしゃり、活動が定着してきていることが伺えます。鍼灸治療の体験や体をケアすることの大切さを知ってもらう良い機会ですので、今後に繋がるよう活動を続けていきたいと思います。
【報告者 北播磨地区:清次容子】
2025/01/09
《西宮地区講習会》
令和6年11月17日(日) 西宮市関西盲人ホーム昭和寮に於いて、西宮鍼灸マッサージ師会の研修会が開催されました。加古郡稲美町「はりきゅう尚庵」の山口尚代先生を講師にお招きして、テーマは「お灸療法 知熱灸を取り入れよう!」です。西宮市だけでなく市外からの先生も含めて15人の参加でした。
最近お灸の良さが見直され夏期大学でも取り上げられてはおりますが、使われるお灸はほとんどがセンネン灸などの台座灸です。モグサを指先で捻って直接体に据える透熱灸や知熱灸は、開業鍼灸師の間でもあまり使われておらず、聞いたことはあるけど見たことはない、とか知っているけれど使ったことがない、と言った先生方がほとんどなのが現状だと思います。山口先生は大阪の松浦鍼灸大学堂で5年間、お灸を中心とした鍼灸臨床の修行をされ、その後ご自身の鍼灸院でもお灸を活かした施術をされています。
前半はパワーポイントを使って、お灸についての説明や臨床においての使い方、よく使うツボの解説などをしていただき、後半は普段使っているお灸のセットを使っての実技をしていただきました。模擬患者役をされた先生は知熱灸を受けたことがない方で、山口先生のお灸を体験して「これが本当のお灸なんですね!」と驚かれた様子でした。山口先生の知熱灸は、半米粒 米粒大のモグサを据えて線香で火をつけ、それが八分くらい燃えたところでその上に次のモグサを重ねるというやり方で、これを5壮から10壮くらいまで繰り返します。1壮ずつ消すやり方に比べはるかにスピーディーで、手際の良い施術でした。実際に寝違えて首が痛いという人に、この知熱灸をすると首の痛みが軽減して可動域が広がったというのも目の当たりにすることができました。
最後は分かれてお互いに練習をしましたが、当然のことながら上手く出来ず、山口先生の技術の高さを認識いたしました。その翌日から私の鍼灸院でも(山口式の)知熱灸を取り入れています。初めのうちは手際が悪く何人かの患者さんに熱い思いをさせてしまいましたが、施術後に肩や腰が軽くなったと言った反応がありましたので、これは効果があるなと実感しているところです。
鍼灸院という看板を掲げているにもかかわらず、お灸はあまりしていない先生がほとんどだと思います。お灸はとても効果があるだけでなく、お灸を据える時間が患者さんとのコミュニケーションになるとこや、お灸の香りや煙が漂っている雰囲気が癒しの空間を作ります。山口先生のお灸愛に触れて、私もそのスタンスがとてもいいなと思いました。私の鍼灸院もお灸の香りが漂う憩いの場にしたいと思います。お忙しい中にもかかわらず資料を準備してご講演いただいた山口先生ありがとうございました。またご参加の先生方お疲れ様でした。これからも鍼灸マッサージを盛り上げて行きましょう!
【報告者 西宮地区:杉輝章】
2025/01/09
《姫路ブロック臨床研修会》
令和6年11月17日(日)午前10時より姫路市民会館5階第1教室にて、宝塚医療大学講師の岡田岬先生にお越しいただき『消化器疾患と自律神経の関係~鍼灸治療のメカニズム~』を講演していただきました。岡田先生は鍼灸師の免許を取り、臨床現場を経て研究の道に進まれた方です。鍼灸がどのように身体に影響をもたらしているのか興味を持たれ、ラットを用いて鍼灸のエビデンスを大学で研究をされています。
■消化器と自律神経:神経系の基本では中枢神経系(脳・脊髄)と末梢神経系(体性神経系・自律神経系)の大きく二つに分かれる。そして末梢神経系は体性神経系と自律神経系に二分される。その自律神経系もまた求心性(内臓求心性神経)と遠心性(交感神経・副交感神経)に二分される。内臓求心性神経は内臓感覚を脳や脊髄へ伝える神経であり、交感神経や副交感神経と同じ神経束内を並走する。内臓感覚は臓器感覚と内臓痛覚に分かれる。臓器感覚(空腹、口渇、便意、尿意)は主に迷走神経・骨盤神経といった副交感神経を通る。内臓痛覚は主に交感神経を通る。消化管に分布する自律神経のうち、交感神経は『闘争または逃走』の機能を有し内臓の消化機能を抑制し骨格筋にエネルギーを送る。一方の副交感神経は『休息と消化』の機能を有し消化機能を昂進させる。特に内臓求心性神経は迷走神経を通っていることもあり、耳の穴付近(迷走神経が分布する)の刺激が効果的である。例えば、耳を温めることや、テイ鍼などの柔らかい刺激をすることで、自律神経を安定させ、内蔵を安定させる効果が期待できる。
■消化器に対する鍼のメカニズム:鍼刺激は胃運動にどのような影響を与えるのか?手、足などの末端部からの刺激は副交感神経を使っており、胃の運動を促進させる。逆に体幹からの刺激は交感神経を使っているために胃の運動は抑制される。具体的には『曲池や足三里』などの手足末端のツボ刺激は胃運動を促進させ、『膈兪、肝兪、脾兪』のいわゆる胃の六つ灸は体幹のツボ刺激であり胃の運動を抑制させる。よって、消化不良などの胃の動きが悪い時には曲池や足三里を使うことが効果的であり、逆に胃痛などの過剰な刺激を落ち着かせる時は胃の六つ灸を使うのが効果的となる。胃痛時に胃の六つ灸を使うのが効果的と述べたが、大学での授業時に「何故、胃の六つ灸に胃兪が入っていないのか?」という質問を学生から受けたことがある。これに関して体のデルマトームを参照にすると、Th12(胃兪)の神経支配は胃の辺りを支配をしていないことが関係していると思われる。
【報告者 姫路地区:佐藤暢彦】
2024/12/02
《第34回 加古川ツーデーマーチ》
11月9日(土)、10日(日)の2日間、加古川市役所を中心とした加古川市内にて、「第34回加古川ツーデーマーチ」が開催された。距離は20km、10km、5kmの3種の設定がされ、年代問わず参加がしやすい様設定がされていた。コースの各所に設置されたチェックポイントでも様々なイベントが開催され、会場全体としてゆったりと楽しんでいる空気が流れていた。事前の予報では荒天の可能性が示されていたが、2日間共に快晴で穏やかな日差しの中での開催だった。
今回は、スポーツマッサージに加えて、鍼での施術も参加者が選択できる準備をしていた。また、家庭でのケアのための試供品も提供いただいていたため、施術を受けた方々には施術後に渡していた。
1日目は、ゴール後のウォーカーに対する施術が中心で昼頃から終了時刻である16時頃まで約80名の方が施術を受けた。運動直後なのもあってかスポーツマッサージの希望者が圧倒的に多かった。また、過去の開催時に参加していたウォーカーのリピートも多く見られた。2日目になると、まずは両日参加のウォーカーの出発前の施術希望が増えた。中には10歳以下の児童も含まれ、身体のケアの重要性がより幅広い世代に認識されつつあるのではないかと感じさせた。また、一日目に比べると鍼での施術を希望するウォーカーが圧倒的に増えた。1日目の疲労が残った状態で2日目に参加したウォーカーが多かったようで連日の施術希望も多数見られた。鍼希望者の多くが鍼での治療を受けるのは初めてだったようだが、受けた人の多くが身体が軽くなったことを実感しとても喜んでいただけたようだった。施術中に「〇〇市で鍼灸をやっている治療院はあるの?」といった質問が出ているのも散見した。一度治療を受けたことでウォーカーの中で鍼灸が治療の選択肢に含まれるようになっていっているのではないかと感じられ、とても充実したイベントだった。
【報告者 北播磨地区:賀内淳一郎】
2024/12/02
《第49回にしのみや市民祭り》
西宮鍼灸マッサージ師会では、毎年市役所前広場で開催される西宮市民まつりへ出店しています。以前は、市民の方に無料マッサージ体験をしてもらっていましたが、スタッフ不足と費用対効果の関係で、一昨年から配布物(啓蒙チラシ、会員の施術所リスト、ツボのイラストチラシ、せんねん灸とコリスポットの試供品)のみにしていました。
今年は市民の方一人ひとりに接客をして、主訴を聞き、お灸かコリスポットを選んで体験をしてもらいました。
お灸は初めてで怖いけどやってみたいとの声が多く、65人にせんねん灸の体験をしてもらいました。ほんわりと心地よかった。家でも是非やってみたいがどこで買えるのか?昔やっていて押し入れの奥にしまっているが、出してまたやろうと思う。などの声が聞こえました。
スタッフは6名でしたが、来場者が途切れることなく接客に追われました。今年もせんねん灸とセイリンから試供品を提供してもらい、啓蒙チラシとともにお渡しし、喜んでいただけました。
セルフケア用のテニスボールマッサージ用のボールは例年とても人気で、2個連結50個と1個を150個用意し、使い方のチラシとともにご自由にお持ち帰りくださいとしたところ、またたく間になくなりました。
来年は西宮鍼灸師会と合同で出店できるよう調整していきたいと思っています。


開催日:令和6年10月26日(土)11時~16時
会員スタッフ:6名
お灸体験:65名
凝りスポット体験:45名
【報告者 西宮地区:瀧川敦子】
2024/11/06
《令和6年度 たるみ生き活き保健福祉フェア》
令和6年10月4日(金)9:30より垂水区社会福祉協議会主催の「たるみ生き活き保健福祉フェア」の一環として「はり・マッサージ体験施術」を行った。今年度からは神戸地区と垂水地区が合併したことにより神戸鍼灸マッサージ師会としての体験施術実施となった。
施術者14名(はり担当5名、マッサージ担当9名、ベッド8台(はり3台、マッサージ5台)体制で実施し、受療者数は48名(はり18名、マッサージ30名)だった。当日のキャンセルや当日申し込み等があり結果的には当所予定受療者数の体験人数となった。
私は鍼施術を担当し、6名の施術を行った(1名あたり約30分)。受療者は40代1名、50代1名、60歳以上4名とかなり高齢者層に偏った形だった。事前予約により施術枠がほぼ埋まっていたこともあり会場は盛況だった。施術させていただいた方にお聞きすると、半数以上の方が鍼施術は初めてということだった。その他の方は転居してきて鍼灸院を探しているがどこへ行けばいいかわからないという方もあった。1人あたりの施術時間は30分となっていたが、初診の上、施術後のフォローができないこともあり、効果を実感できる程度の刺激量とし、身体の動きの変化が感じられるよう動作のビフォーアフターを感じていただけるように施術を行なった。
今回、この保健福祉フェアでの体験施術にはじめて参加し、後ほど行なった垂水区社会福祉協議会の方との次年度に向けてのミーティングにも出席し、様々な検討課題があるように感じた。コロナ禍を経て、5年ぶりに再開した体験施術であったが、施術体験希望者への告知、募集方法、施術枠の設定方法や当日の運営に至るまで再検討が必要ではないかと思う。
このような各種のイベントでの体験施術やスポーツイベントにおける医療ケアの一端としてのボランティア施術は鍼灸マッサージ施術の啓蒙普及にも寄与することを期待し、できる限り参加したいと思う。また、体験施術等でご縁をいただいた方がその場だけでなく、どこかの施術院で継続して受療していただけるよう仕組みを考えたいと思う。
【報告者 神戸地区:井上和哉】
2024/10/01
《令和6年度 夏期大学講座2日目》
令和6年9月8日(日)午前の部では『アスリートのコンディショニングに東洋医学を活かす』の演題で明治国際医療大学鍼灸学部 谷口剛志先生にご講演いただいた。
アスリートのコンディショニングで『治未病』の概念を活用して精神面・肉体面・健康面をアプローチするのは、斬新的で大変良かったと思います。
アスリートのコンディショニングを主観的な指標(VAS)と客観的な指標(唾液コルチゾール濃度)で捉えて、その上で募穴診を行い、圧痛を指標にコンディショニングの変動を捉えることができるのかを検証したのは目新しい情報です。スポーツ鍼灸の発展を願います。
午後の部では『冷え性の診断と治療』の演題で関西医療大学保健医療学部はり灸・スポーツトレーナー学科 坂口俊二先生にご講演いただいた。
臨床の場面では、冷え性の主訴よりは愁訴で来院されると思います。患者の満足度向上に以下のセルフケアがヒントになります。
今回、教えて頂いた冷え性の対策でセルフケアとしては、湯たんぽを大腿部に置いて作業をすると足が冷え難い坐業でない場合、使え捨てカイロ固定用のホルダーを活用して、後頚部や肘部に当てると手の冷えの程度が軽減する。
就寝前の足三里、三陰交、湧泉への間接灸を続けると良い。

【報告者 神戸地区:伊藤傑】