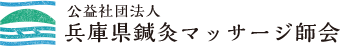2024/12/20
兵鍼会報257号(2024年12月発行)
以下、テキスト本文です。
【第23回東洋療法推進大会in徳島参加報告】
第23回東洋療法推進大会in徳島が、9月29日(日)・30日(月)の両日、徳島グランヴィリオホテルにて「新たな潮流・生み出す未来」を大会テーマに掲げ盛大に開催された。本会からは、執行部(賀内・天野・木村・小川)、理事(櫻井・山口)、宇仁菅が現地参加、中村事務長がズーム参加した。
開会式では、長嶺全鍼師会長・高島徳島県師会会長・徳島県知事秘書・遠藤徳島市長より会場にて、自見はなこ内閣府特命担当大臣・伊佐進一前厚生労働副大臣・松本吉郎日本医師会会長よりビデオにてご祝辞をいただいた。
《初日》
特別講演(1)では、「現代人の抱える不調と東洋医学の可能性」の演題で徳島県出身の元日本テレビ記者「情報ライブミヤネ屋」コメンテーター等で活躍中の丸岡いずみ氏の講演を拝聴した。
丸岡氏は東日本大震災時に「うつ病」を発症し、回復後うつ病に関する啓蒙活動中に心療内科医より「心療内科と鍼灸は相性がよい」と聞き、鍼灸と心療内科が併設するクリニックで初めて鍼灸を体験した。
そこでまず驚いたのは、西洋医学なら数分で終わる診療も、問診に1時間、施術に1時間掛けると言う点。更に驚いたのは鍼灸師が大学の後輩だったとのこと。
そして、問診より「冷え症」に対する鍼灸治療を受けた。鍼に関しては痛みは無かったものの効果の実感は得られなかったが、お灸は自身が思っていた艾に火を付ける物ではなく、ローラーのような物でお腹の周りをクルクル回す施術を受け、身体がポカポカして寝てしまいそうになるほど気持ちが良く効果を実感出来たと言う。その後、食生活や生活習慣のアドバイスを受け、治療と言うよりも相談に乗ってもらったと言う印象が強かったとのこと。また、鍼灸の問診は心理学のアセスメントに凄く近いと感じたそうです。
次に少し話しを掘り下げ、そのクリニックで行なわれている「鍼灸と睡眠」についての知見を紹介された。女性60人を対象に月4回平均鍼施術を行ない、寝付き・途中覚醒・総合睡眠時間・睡眠の質等、全てにおいて改善が見られたと言う研究結果が出たとのこと。
日本人の平均睡眠時間は調査した33カ国で最も短く7時間22分。最も長かった国は南アフリカの9時間13分。33カ国の平均が8時間28分。睡眠が短ければ仕事にも影響が出る事から西洋医学的には睡眠導入剤を処方される。高齢者の断薬は難しく東洋医学の効果を期待しているとのこと。また、最近はうつ病に漢方薬を処方される医院も増えてきており、東西医学を併用した治療現場の声も聞くようになった。
著書「休むことも生きること」は実体験を含め5人の医師の監修のもと出版されたが、鍼灸を体験する前だったので、今後は東洋医学の良さを世に発信し貢献できればと思っているとのこと。
詳しくは東洋療法363号(11月発行)をご覧ください。
特別講演(2)では、昨年に引き続き関西医療大学フェムテック寄付講座 特任教授 菅万希子先生による「フェムテックに鍼灸マッサージを~やさしいAIとNudgeで実現できる~」を拝聴した。
(フェムテックとは、女性の健康の課題をテクノロジーで解決する製品やサービスのことで、「female technology」を略した用語。)
女性特有の症状や更年期等の不定愁訴に対し、西洋医学は、大丈夫であることを納得させるために検査を沢山行うが、そもそも不定愁訴は他覚的所見がないものであるから、検査結果を以て疾病を特定することができない。
不定愁訴は疾病ではないので主観的評価の改善でよいが、改善の機序は明らかにされるべきと考え、産学連携で西洋医学の補完を東洋医学ができる機序をAIで明らかにする取り組み。その為にアンケート調査を行い、ひとつでも多く集め分析し、効果の高い治療穴をAIにより検索できるプログラムを構築し、鍼灸師にフィードバック出来るシステムを作ることで業界がより良くなるのではないかとの思いから研究している。
※アンケートの注意点として、患者さんには施術の前後にアンケート回答依頼し、施術者回答は患者さん1人につき1回のみとする。患者さんには施術者を気にせず回答してもらうこと(忖度があってはならない)。
現在も全国の鍼灸師にアンケート調査を実施中。今までの回答をAIで解析したところ不眠とストレスの効果ありと判断がなされている。調査で明らかになったことは、意外と施術環境(内装)他が重要であることが分かった。今回の調査で環境が左右することが分かったので、環境についての追加研究が必要との見解。
保険講演では、全鍼副会長で保険委員長の往田和章氏による「令和6年度あはき療養費の料金改定について」を拝聴した。
- 往療料の解釈変更について(令和6年10月からの解釈)
・往療料と訪問施術料に分離
往 療 料:突発的に通所できない患者に対して患家に出向いて施術した場合
訪問施術料:通所できない患者に対してあらかじめ施術者と患者の間で施術する日程、頻度を申し合わせて施術に出向く場合
例)同意済の傷病又は症状の悪化により通院できない
自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難
・はりきゅうは同意書があれば算定
・往療料 突発的な状況下で算定(1回算定したら14日は算定不可)
・医師の連携必要 同意書にその旨記載
・14日以内の再患家は訪問施術料
・同一日同一建物の場合は、誰か一人に往療を算定
・訪問施術料 同日同一建物への訪問施術は患者の総数で算定
(何回かに分けて訪問しても、あくまでその日の総数で判断する)
・患者総数は施術者単位ではなく、施術所単位で
・違う施術者が午前と午後に2名の同じ患者に施術した場合は、患者4人(訪問施術料3)で算定する
・自費の患者は考慮しない(保険使う人のみの算定)
・施術者数は延べで考える
・施術所ごとの算定になったことで、有資格者の処遇が悪くなる
例えば大規模特養等に複数有資格者で出向いた場合でも、施術所ごとだと施術者単位の支払が少なくなってしまう
・特別地域 全鍼のHPに掲載予定
- 支給申請書記載のポイント(10月から新様式で、旧様式は使用不可)
(厚生労働省HPまたは全鍼HP会員ページよりダウンロード)
・認知症のみの同意書傷病名の場合、マッサージを行っているのであれば、知り得た範囲内で傷病名を追加すること(同意書に記載された傷病名では「適応疾患なし」と審査されるため)
・業務上・外、自賠責にはマルをしないこと
・傷病にいたった理由は「不詳」と書くこと
・施術した場所 患者の住所が保険証記載と異なる場合に記入
保険証が老人ホームの場合は記載不要)
・施設名を必ず記入すること→施設に入っていることを隠さない。
・「傷病名および症状」になった理由
2か月以降は同意書添付がないので、傷病名だけではどこに症状が出ているかわからないため。書ききれない場合は摘要欄に書く。
(摘要欄の活用記入例は全鍼HPに掲載予定)
・書ききれない傷病名および症状例
施術管理者以外が施術した場合は、施術者名と施術日
往療料は連携医師名と日
鍼灸・マッサージ両術の日
患者が署名できない場合、患者以外の署名の場合の理由
摘要欄に書ききれない場合は別紙を添付(摘要欄に別紙ありと記入)
・特別加算は全員につけられる
・施術回数欄は5部位施術数と3部位施術数の合計を記入
・料金は5部位と3部位を分けて2段書きする(回数は合計)
・1術と2術も2段書きする
・徒手矯正施術も施術回数欄には各部位回数の合計を合算する
・施術内容のカレンダーには施術内容一覧のとおり○◎①~③を記入
(◎の時は摘要欄にも記載)
《2日目》
- シンポジウム① 組織・将来ビジョン等検討委員会
今回のテーマである「新たな潮流・生み出す未来」を題材に全鍼執行役員と日鍼会理事とでパネルディスカッションを行なった。
■フェムテックについて
・エビデンスを持った施術を行なうことで同意書の問題や保険交渉が行ないやすく、明るい未来が見えてくるのでは?と考える。しかし、アンケートの回答が少なすぎるので是非協力をお願いしたい。(アンケートは2分程度で終わる)
・政府はフェムテック事業に毎年補助金を付けている。
・フェムテックはデンマークで作られた造語で、経済産業省が行なっている国の施策である。
・厚生労働省では、まだフェムテックについて造詣が深くないと感じている。
・海外では鍼灸の有効性がかなり認められてきたが、日本ではエビデンスが無ければ相手にしてもらえない傾向にある。
・今回のアンケートは、ある意味患者様満足度調査である。
■鍼灸電子カルテの標準使用の策定に関する会議(6団体)
・レセプト請求に関しては99%電子請求
・電子カルテにおいては統一が非常に困難
・電子カルテ普及状況(令和2年)
一般病院 57.2%
(病床数が多い病院ほどパーセンテージが高い)
・鍼灸における電子カルテ
電子・紙のいずれか使用 90%増
紙カルテ 70%
電子カルテ 14%
併用している 15%
■全鍼協同組合
・クラウドサービス 設計中
・購買、共済、教育、電子カルテ事業等を一本化する事業
・アンケート結果はHP参照
・同一症状でも治療方法は様々→動画撮影の協力・承諾を願いたい
①会員増強と組織強化
・紹介制度=紹介者も紹介された者も会費半額
・今年キャンペーンを使った成果はまだ出ていない(総会で発表)
・県師会の会費も半額にしている所としていない所がある
・紹介した先生の会費を無料にしては? の意見あり
■会員増強について
・会費見直しと組織合併
・実務研修の受け入れによる新規入会
・地域連携とPR活動
・教育機関との連携
・業界説明会、業団説明会の実施(式典への出席)
・教員との会合、学生へのLINE登録推奨
・キャンペーンの実施
・個別勧誘とコミュニケーション
・政策提言と組織運営の見直し
・教育・奨学金制度と次世代育成
②会員の収入を上げるためには?
・療養費経営についてのアンケート(途中経過 134名)
ひとり施術者 72.4%
マッサージのみの施術所 14.9%
大部分がマッサージ 27.8%
鍼灸とマッサージ半々 21.6%
鍼灸のみの施術 19%
・施術者ひとりあたりの売上は?
20万以下 33.6% 21~50万以下 34.3%
・収入から会費を払う余裕がない?
・施術所の一番の悩みは?
新患が取れない 1位
・月平均新患は?
マッサージ 0人 31.8% 1~2人 59.1%
鍼灸 0人 22.3% 1~2人 61.1%
・あなたが必要としている情報は?
・療養費についての最新情報 54.1%
・医師や看護師等他職種連携の知識52.6%
※所得水準をいかにして上げていくかが課題
■質疑より
・予約システムの構築は時間の管理、無駄の削減になるので有用
(業者の選定は必要だが、費用は10万~20万円程度)
※協同組合:予約だけでなく、新規獲得も同時に行えるシステムを考えている
・業務の構造改革が必要 鍼灸マだけでは収入不足
(社会福祉士免許等、他業種の免許も必要)
(弁護士、司法書士、大学病院〈精神科〉等をターゲット)
※全鍼:鍼灸マだけで食べていける基盤をつくるのが役目と考えている
・キャンペーンで栃木県は6名の会員を獲得、しかし事務処理が複雑だったので簡素化を求む
・国家資格のパワーが足らない部分を経営力で補えるよう全鍼に指導を乞いたい
※往田:仕事の分担化で効率アップ
・大阪では鍼灸フェスを開催して埋もれている鍼灸師の入会開拓を考えている
・長嶺:公益社団だから国との交渉にも臨める
(非会員も恩恵を受けるので、有資格者は入会するのは当然と考える)
■鍼灸マッサージの魅力をどのように伝えるか?
・ターゲットの明確化
・SNSとメディアの活用
・体験を通じた魅力の発信
・京都:医療関係に講座を受けた鍼灸師の名簿を出し、同意書作成等のお願いをした。
高齢者住宅に送り込める環境作りを構築
会員のために動くのが役員の役目
- シンポジウム② 法制委員会
「広告ガイドラインと無免許問題」をテーマに厚生労働省医制局医事課より、シンポジストに柳田聡専門官をお招きして開催された。
広告ガイドラインは平成30年に発案され、7年を経てようやく一歩前進した。
無資格者をあはき法で取り締まるのは非常に難しく、広告ガイドラインに明記する形を取った。
- 広告可能な事項の具体的な内容
・国家資格の種類
・治療院(但し、施術業態を明記すれば可能)
・施術所の住所・電話番号・施術日・施術時間
・開設届出済・保健取扱・予約・出張・駐車場の有無
- あはき・柔整に関する内容に該当しない事項(禁止広告)
・診療・診察
・施術者の技能・施術方法・経歴
・あはき、柔整に関する内容にないもの
・広告可能以外のもの
- 相談指導について
・都道府県等において相談窓口の設置
・消費者センター等との協力
・都道府県から厚生労働省へ相談
- インターネット上のウェブサイト
・料金・施術内容や時間・主なリスク(副作用)等は可
・掲載すべきでない事項
虚偽 誇大 費用の過度な強調
他との比較による優良性を示すもの
早急なサービスを過度にあおるもの
- 無資格者の行為に関する広告について(禁止事項)
・国家資格を持っていると誤認するような表現
・特定の疾患に対する施術
・疾患の原因となる可能性を含んでいる症状の施術
※広告規制事項を掲載した場合、広告業者(ホットペッパービューティー等)、施術所両方の罰則となる
厚労省は、リラクゼーションを取り扱っているような広告事業者との意見交換も実施しており、今回の広告ガイドラインも提示して一定の理解を求めているとのこと。
今年度は、初めて予算事業で国家資格を有する者の施術の素晴らしさを示す広報を企画しており、有資格者と無資格者の違いがわかりにくいことから、業界の意見を聞きながら広告媒体を考えているとのこと。
次に質疑応答があり、会場からは多くの意見や質問が問いかけられ、専門官や執行部がそれに回答し、充実した2日間を終えた。
来年度は、9月28日(日)・29日(月)、石川県金沢での開催。
報告者 小村 豊
【広報部からのお願い】
広報部では、毎月発行しておりますmAm(マム)以外にも、臨時情報として細かく情報を開示しております。昨年度は臨時情報として39回配信しております。勿論、県師会のホームページにもアップさせていただいておりますが、一早く情報を受け取りたい方やホームページを見るのが苦手な方は、是非メールアドレスの登録をお願い致します。また、パソコンをお持ちでない方でもスマホは持っていると思います。携帯のメールアドレスで構いませんので、登録をお願い致します。。
※登録先
mail:info@mam-hyogo.or.jp
件名:mAm配信希望
本文:所属地区名と氏名をご記入の上、送信してください。
また、パソコンに精通されている方は、ホームページ画面上のお問い合わせからお願いします。その際、ご相談内容の欄に「メールアドレス登録希望」と入力してください。
注)「迷惑メール防止設定」をされていると事務局からのPCメールが受信できませんので「設定を解除」されるか「指定受信設定」にして下さい。
宜しくお願い致します。
★夏期大収録DVDについて
本年度も学術講演会(夏期大学講座)の収録DVDを1,500円で販売しております。内容は、2日間の録音(mp3)に加え写真(JPG、実技の一部を動画(MOV)、兵鍼講座46(docx)も納めております。プレクストークや.mp3対応CDプレイヤーで聞かれていた方には視聴出来なくなりますがご理解の程、宜しくお願い致します。
尚、パソコンでの視聴とはなりますが、購入後ご自身でデータを移しプレクストークや.mp3対応プレイヤーで聞く事は可能です。
収録DVDのご購入は県師会事務局までご連絡ください。
《夏期大学講座報告》
(1日目)
報告者:神戸地区 井上和哉
令和6年7月14日(日) 10時30分より令和6年度夏期大学講座1日目が開催された。
午前の部は【お灸堂】院長 鋤柄誉啓 先生をお招きし「灸治療院の診療及び活動の
ご紹介」との演題でご講演いただいた。
鋤柄先生が普段行っておられる施術のご紹介とともに患者といかに寄り添っていくかということについての工夫がよく伝わってくる講演だった。講演の中で私が印象的に感じたこととして、鋤柄先生が施術のことを「お手当」と表現されていた点と施灸による身体変化をきちんと患者と共有していた点である。医療の原点は症状に対して手を当てることから始まったと言われており、まさに、それを実践されているということだろう。また、昨今は慢性症の患者が増加しており、症状寛解にすぐに至らないケースが多いが、身体の変化をきちんと認識し、それを積み重ねていくことで身体の状態が改善していくことを丁寧に伝えておられるとのこと。患者目線で施術者が歩み寄り、患者に寄り添う施術を継続して実践されている。このようなことは施術者としてのキャリアが長くなると希薄になっているのではないだろうか。施術者としてのスタンスを再考するいい機会になったと思う。
午後の講演は【京都四条からすま鍼灸院】中島美和 先生をお招きして、「頚肩上肢症状に対する鍼治療」との演題による講演と実技供覧だった。
鍼灸施術は様々な技法、手法があり、選択肢が多いという点では強みになる一方、それらは先人の経験に基づく伝道であり、体系化されておらず、鍼灸施術の受療率が上昇しにくい要因となっている。今後はさらに基礎研究がなされ、EBMに基づく医療技術であることがもっと発信されるべきと中島先生は述べておられた。
上記を踏まえ、頸肩上肢症状の発症要因として最も多い、頸椎の退行変性を基盤とする運動器障害について、症候、疾患の成り立ち、さらには治療法を理解する上で必須となる、頸椎の機能・解剖、診察技法等についての講義が行われた。特に神経分布については詳しく解説していただき、神経へのアプローチでは、どの部位に鍼をどの方向に、どの程度の深度で刺入すれば効果が期待でき、また安全に刺鍼できるか等、非常に詳しく講義していただいた。多くの受講者が養成施設を卒業して長い時間が経過しており、また養成施設での解剖学の講義よりも詳しく、脳に汗をかいた方も多かったのではないだろうか。知識の再認識と学び続けることの重要性を再確認するよい機会となった。
また、実技供覧においてはモデル患者に対し、講義でお話いただいた刺鍼部位に実際に刺鍼し、鍼の刺入方向や深度が確認できた。今回は時間の制約もあり、視力の弱い方には触知して確認する等は難しかったが、詳しく説明をしていただきながらの実技供覧でイメージはできたのではないだろうか。
私的には解剖学の知識は有害事象を招かないためや、他の医療業種従事者との情報共有において共通用語を理解、使用することは不可欠と考えるが、本来の東洋医学の強みを活かすためには、現代医学の知識に経絡経穴や東洋医学の臓器感などが融合できてこそ本来の力を発揮できるのではないだろうか。今後の研究に期待したい。
(2日目)
神戸地区 伊藤 傑
メインテーマ:現代人に寄り添う東洋医学
『アスリートのコンディショニングに東洋医学を活かす』
アスリートのコンディショニングで『治未病』の概念を活用して精神面・肉体面・健康面をアプローチするのは、斬新的で大変良かったと思います。
アスリートのコンディショニングを主観的な指標(VAS)と客観的な指標(唾液コルチゾール濃度)で捉えて、その上で募穴診を行い、圧痛を指標にコンディショニングの変動を捉えることができるのかを検証したのは目新しい情報です。スポーツ鍼灸の発展を願います。
『冷え性の診断と治療』
臨床の場面では、冷え性の主訴よりは愁訴で来院されると思います。患者の満足度向上に以下のセルフケアがヒントになります。
今回、教えて頂いた冷え性の対策でセルフケアとしては
・湯たんぽを大腿部に置いて作業をすると足が冷え難い
・坐業でない場合、使え捨てカイロ固定用のホルダーを活用して、後頚部や肘部に当てると手の冷えの程度が軽減する。
・就寝前の足三里、三陰交、湧泉への間接灸を続けると良い。
“夏期大アンケート紹介”
本年度も多くの方にアンケートをお書きいただきありがとうございました。
以下に2日分のアンケートを集計し、抜粋したものをご紹介します。
(アンケート総数:48名分)
※全文は長いので一部抜粋して掲載します。
(1日目) (2日目)
- あなたに該当するものを選択してください
・兵庫県鍼灸マッサージ師会会員 19名 11名
・その他の都道府県鍼灸マッサージ師会会員 1名 0名
・その他の鍼灸マッサージ業団体所属 0名 0名
・各種学会所属 0名 0名
・養成施設や専門学校の教員または学生 6名 4名
・一般 4名 2名
・無回答 1名 0名
- あなたに該当するものをすべて選択してください
(グーグルフォームの設定ミスで一つしか選択できず)
・男性 (1日目) 8名 (2日目) 9名
・女性 16名 4名
・無回答 6名 4名
・年齢 20歳代 0名 1名
・ 30歳代 2名 2名
・ 40歳代 3名 0名
・ 50歳代 8名 8名
・ 60歳代 7名 4名
・ 70歳以上 3名 1名
・無回答 8名 1名
・晴眼者 6名 4名
・視覚障害者(弱視) 4名 2名
・視覚障害者(全盲) 2名 2名
・無回答 18名 9名
- 午前の講座に満足した点をお書きください
(1日目)
・お灸専門院の治療の流れ
・町の鍼灸院ができることのヒントがたくさん
・先生の治療院でされていること、現代の患者さんの悩みに不定愁訴などがよく分かりました
・治療院でお灸しているので、とっても勉強になりました
・SNSやグッズの話が面白かったです
・灸治療のやり方が参考になりました
・セルフケアの重要性を通観しました
・灸の利点を再認識した(鍼とは違う意味で)
・臨床に使ってみたいと思う内容だった
・お灸に力を入れてみようと思った
・細かく丁寧な説明
・お灸を身近なものに感じることができた
・お灸治療について詳しく聞ける機会は少ないので、とても勉強になりました
・とてもわかり易く、自分とは違う目線からの意見が取り入れられそう
・啓発活動の内容がしれた
・お灸について、詳しく知ることができたし、患者さんへの寄り添い方も学べました
・院内の設備が良かったです
・患者さんへの発信の仕方がSNSを使って普段の治療時間では足りない事を説明やアドバイス出来るように使うのは非常に有効だと思いました
(2日目)
・鍼灸の可能性についての説明が良かった
・募穴診を行っていること、興味深く実践できそうだった
・コンディショニングに鍼灸が役立つ可能性や考え方が広がった、提案できることが増えた、スポーツ分野はあまり得意ではなかったので勉強になりました
・最近ランニングをやっているので疲労がたまりやすい所などの説明があり分かりやすかったです、西洋医学の話も聞きたいです
・自分の身体を見つめることの大切さがわかった
・コンディショニングという技術がまだまだ未熟だということの再発見
- 午後の講座に満足した点をお書きください
(1日目)
・詳細な解剖学や臨床での鑑別ポイントが非常に勉強になりました
・基礎から学べたし、内容が豊富だった
・解剖学的なものをすっかり忘れていましたが多くの気づきがありました
・実技も見られてよかった
・内容がわかりやすかった
・頚肩の難しい神経の勉強になりました
・内容が深く、説明が詳しい
・大変わかりやすく自分の治療を見直す点が多い
・頚椎の詳細な解剖学が学習できたこと
・実際の施術を見ることができた。解剖学の復習ができた
・お話が専門的でとても刺激になりました。 筋肉、支配神経、神経の走行…勉強を頑張ります。 また、実際に鍼をうちながらの説明も聞けてとても勉強になりました。
(2日目)
・私もとても冷え性なので鍼灸を受けてみようと思った
・テキストに沿って分かりやすく説明してくださったので良かったです
・学んだ事柄をすぐに実技にて体得できたことに満足した
・大変丁寧に説明していただき分かりやすかった
・冷えの内容が今すぐ使える具体的な配穴等わかりやすかった
・日頃から疑問に感じていたところが解消しました
- 本講座について改善点やお気づきになった点、ご要望などご意見があればお書きください、
(1日目)
・午前中は声が聞き取りにくかった
・お二人の先生方のパワーポイントのコピーがあればすごく助かったと思います、聞きながら書くのが大変で書くことに集中してしまって、もっと聞きたかったです
・ズームによる開催も検討してほしい
・せっかく素晴らしい内容に併せて作っていただいているスライドが全く見えないのが残念でした
(2日目)
・資料のテキストデータが欲しかった
・質疑応答の時間をもう少し設けてほしいです
・午前の部は終了10分前ぐらいから質問の時間にあてるなどしてくださる方が助かります(昼食時間が短くなり外食などすると時間が気になったので)
・オンラインでの受講も可能にして欲しいです
・エアコンの調整をこまめにして欲しい、時間厳守で進行してほしい
・質疑応答の時間を1時間ぐらい欲しいです
- 本講座で今後取り上げて欲しい内容(伝統鍼灸、現代鍼灸、不妊鍼灸、美容鍼灸、手技療法、漢方医学、養生学、精神医学など)や講師の推薦などがあればお書きください
・不妊治療
・SNSを上手に活用している方(鍼灸院の宣伝などを上手にしている方)・
・伝統鍼灸
・現代社会の動きにフィット(適合)していける理論などが盛り込まれた講座
・現代鍼灸、手技療法、精神医学、漢方医学
・お灸の実技講習(越石式灸)
・お灸体験やあんまについて
・美容鍼灸、自律神経
・頭痛、座骨神経痛、膝痛
・曲直瀬道三
・北小路先生
・東洋医学の真髄 脇岡望文先生
・日本の伝統鍼灸に関する話題、松田博公さん
・伊藤和憲さんのトリガーポイント
- 本講座をお知りになった媒体を教えてください
(1日目) (2日目)
・兵庫県鍼灸マッサージ師会ホームページ 7名 7名
・他のウェブサイトまたはSNS 1名 0名
・月刊東洋療法、兵鍼会報、月刊情報mam 11名 4名
・本会会員の紹介 7名 3名
・その他(利用者、会員、学校で案内あった) 2名 3名
・無回答 3名 2名
- その他、ご意見ご要望などご自由にお書きください
・解剖学や生理学の講義はレジュメ(スライド)が手元に欲しかったです、メモを書き込みながらでないと理解や書き取りが追い付かず聞き流すだけになりがちなので
・感染症対策にはご留意ください、マスク着用など
・今日の室温は比較的適温でした(場所による?)
・午前の部が冷えすぎ(会場後方)
・いつも良い講座していただきありがとうございます、興味ないな~って思う講座でも参加するとすごく勉強になり帰って治療に取り組むと効果が上がります、とっても大切な時間だと思います
★受講状況(トータル77名)
1日目:受講者:42名。(内訳:会員25名。賛助会員1名。学生6名。一般10名。)
2日目:参加者:35名。(内訳:会員23名。賛助会員1名。学生3名。一般8名。)
★夏期大学講座2日間、12単位取得者
今年度、取得された11名の方をご紹介します。
天野 豊(姫路)、板垣陽子(神戸)、井上和哉(神戸)、小川結子(神戸)
賀内進一(北播磨)、賀内淳一郎(北播磨)木村慎一(神戸)
櫻井義明(明石)、杉 輝章(西宮)、松本研吾(神戸)、横山善人(西宮)
【第7回DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会に参加して】
2024年7月28日、履正社国際医療スポーツ専門学校体育館にて、第7回災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会が開催されました。今回は実技を中心にした内容のため現地参加のみで行われ、十三駅から炎天下を徒歩5分、汗びっしょりになって会場に到着しました。
DSAMとは、災害時に支援ができる鍼灸師・マッサージ師の養成と、発災時に行政や関係医療団体等に対する業界の窓口となることを目的として、2018年に全日本鍼灸マッサージ師会と日本鍼灸師会が合同で立ち上げた「災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会」の略称です。今回で7回目となる講習会は、令和6年能登半島地震での活動報告、ダンボールベッドの組み立て体験、DSAM隊員として即戦力となるための支援活動の実習という内容で行われました。
基礎講座「令和6年能登半島地震 DSAM活動報告」では、DSAM代表 是元佑太氏、副代表 仲嶋隆史氏から、「今回の活動はこれまでとは大きく異なっていた。」との報告がありました。
「発災直後にDMATから要請を受けたが、もっと早く現地入りしてほしかったと意見された。石川県庁職員が夜通し寝ずの番で安否確認等の電話応対に追われ疲弊しているので支援してほしいとのことだった。そして、石川県庁内に設置されたDMAT本部にDSAMの活動拠点が設けられて活動を開始。JIMTEFでの研修が現実になり、顔が見える関係の重要性を感じた。本部に拠点があることで刻々と変化する需要をリアルタイムに把握することができ、生の声をダイレクトに聴くことができた。支援者支援の施術ブース増設等の交渉事も面倒な書類のやり取りを省略し即OKとなった。
1月17日までは石川県庁にて活動を行い、それ以降は志賀町役場避難所、富来活性化センター、七尾・能登中部保険福祉本部、輪島市役所災害対策本部、珠洲市役所等4市1町で約4か月間活動を実施。その間、輪島市では避難所格差の情報が流れ一部暴徒化し荒れていたり、子どもへの虐待があったりと、避難者同士の問題が多く発生し避難所での支援が難しくなった。経験したことがない問題が沢山起きた。避難所支援を中止し被災者支援に切り替えることにした。市町村役場や関連施設に赴いて毎回施術ブースを設置し、訪れる被災者や支援者に施術して、終わればすべてを元通りに片付けて帰るため、珠洲市へ赴いた際は真っ暗な早朝に石川を出て深夜に帰ってくる等大変な活動であった。
支援者1人が倒れると避難者10人が倒れるといわれるほど、支援のコーディネートは難しい。」とのことであった。
受療者数等は、石川県庁では支援者支援(DMAT隊員、行政職員、警察官、自衛官、消防士等)18日間、施術者のべ94人、受療者のべ267人。いしかわ総合スポーツセンター1.5避難所(DSAM担当)では、被災者支援12日間、施術者のべ92人、受療者のべ352人であった。 志賀町富来活性化センターでは、コロナの隔離病棟のようになっていて落ち着くまでは活動不可だった。高齢者や持病のある人が多く鍼経験のある人も多かった。期間の途中から自宅片付け等へ出て新たな主訴が出た。
今回の活動を踏まえて、今後は超急性期に支援の展開が必要であり、今までは避難者支援が主だったが支援者支援も重要であり、支援者支援の目途が立てば地元師会に任せて撤退するという流れが良いのではないか。
また、輪島市の暴動のように待遇の違いが避難者の心を乱さないように、避難者を公平に扱い、施術者は共通の認識を持つこと、決して普段の治療と混同しないよう注意が必要である。実際にあった問題行動には、次のようなものがある。設備の使用許可を勝手に出す。服のうえから刺鍼する。他人の施術に口を出す。置鍼中に車中の荷物を取りに行く。長時間の施術。持参した私物のレッグウォーマーを貸し出す。太い鍼をうつ。DSAMの悪口をいう等。
実技では、段ボールベッドの組み立てやポップアップテントの設営・片付けの実演、マスカーと呼ばれる養生テープ(広げると薄いビニールがカーテンのようにひらひら垂れるもの)を使用して簡易施術スペースを設置する方法を実演していただいた。
午後からは、その施術スペース内であらゆる状況を想定して実際に施術を行う実技研修が実施されました。電気、ガスあり、水なし、40世帯100人がテント生活の避難所における被災者支援の想定で、受療者役、受付役、問診役、施術者役に分かれて施術を行った。施術者が共通の認識を持つために、終了後には改善点について説明していただき、話し合った。
質疑応答では、支援活動のマッチングがことごとく成立しなかった理由について、「交通費くらいは助成金の範囲内で支払いたかったので、できるだけ近隣(福井、富山、新潟)の方に依頼した。」との回答があった。
本研修に、兵庫県鍼灸師会の副会長兼学術部長及び広報部長も出席されており、兵庫県と両師会が協定を交わしている兵庫県災害支援鍼灸師の今後の活動について本腰を上げて取り組んでいきたいという意向をお互いに確認することができた。
阪神淡路大震災の時、神戸は返しても返しきれないほどの御恩を全国各地から受けました。現在のように支援網は整っていなかったので真の人情で思いやり助け合っていたと思います。広島からバスごと神戸に入って休みなく毎日毎日鉄道の代行運転をしてくださった運転手さんの疲弊しきった横顔が、私の災害支援活動の原動力となっています。有事に備えての準備は事が起きる前に整えておかなければなりません。災害支援活動にご興味のある方、ご協力いただける方は是非お声かけくださいますようお願いいたします。
報告者 小川 結子
【ハッピーパックのご紹介】
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが情報提供させていただきます。
神戸市勤労者福祉共済制度(ハッピーパック)は、個々の企業で独自に実施することが難しい福利厚生を、市内中小企業の事業主と力を合わせて運営することにより、従業員の皆さんにより豊かな生活を送っていただこうと神戸市が創設した制度で、神戸市が100%出資している外郭団体 公益財団法人神戸いきいき勤労財団が運営しています。
このハッピーパックを施術所等の福利厚生として導入することが可能です。原則、神戸市内に施術所等があることとされていますが、神戸市外でも可能です。施術所等の代表者がハッピーパックに加入し、掛金として従業員(加入員)一人につき月額500円を支払うことで、従業員が様々な福利厚生サービスを受けることができます。従業員のいない一人事業主(施術者)も加入できます。
さらに、このハッピーパックを施術所の広告媒体として利用することができます。ハッピーパック会員が利用できる施設として登録することで、財団のホームページ及び月刊ハッピーパックニュースに無料で広告を掲載することができます。神戸市外の施術所であっても登録は可能です。一度登録すると解約するまでハッピーパックのホームページに掲載されます。また、月刊ハッピーパックニュースの誌面に、新規の利用可能施設として登録時のみ掲載されます。
広告の掲載は無料ですが、条件として、ハッピーパック会員証(加入員証)を提示して来院した方への割引サービスもしくはプレゼント贈呈を行うことが必要です。
また、月刊ハッピーパックニュースに折り込みチラシを持込依頼することも可能ですが、その場合は別途5万円がかかります。
随時、施術所の特別キャンペーン等を月刊ハッピーパックニュースに掲載する事も可能です。この場合も掲載料はかかりません。
★利用するには、神戸いきいき勤労財団に申込む必要があります。
※従業員の福利厚生として導入する場合
財団へ電話を架けて共済への加入手続きを行う。
※利用施設として登録する場合
1.財団へ電話を架けて施術所を登録。
2.兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会会員である事を申し出て登録すると財団からギフト券が進呈される。
3.財団HP・月刊ハッピーパックニュースに利用施設として無料で掲載される。
4.患者様がハッピーパック会員証を提示して来院される。
5.広告に掲載した施術料金の割引もしくはプレゼントの贈呈を行う。
(例:施術料5%割引、初診に限り割引など)
登録先:〒650-0033
神戸市中央区江戸町104番地 (6階)
TEL.078-381-5101
FAX.078-381-5682
<https://www.kobe-kinrou.jp/> 公益財団法人 神戸いきいき勤労財団
【ファミリーパックのご案内】
兵庫県におきましても神戸市同様のサービスがありますので併せてご紹介します。
公益財団法人兵庫県勤労福祉協会共済部が運営しておりますファミリーパック
https://www.family-pack-hyogo.jp/
上記URLにアクセスいただき
ファミリーパック→提携契約を希望する企業様へ→指定店の申込
と進んでいただくと手続きの仕方が掲載されています。
ご興味のある方は、こちらも検討されてはいかがでしょうか。
【企業への参入登録募集】
兵鍼会報 2022年10月号(250号)で一次募集しておりました健康経営に関する登録者は現在6名です。
当初は、兵庫県中小企業団体中央会に出向きチラシ等を設置していただきましたが反応が無くうやむやになっておりました。
この事業も、来年度はもう少し宣伝を拡大し、上記案内の公益財団法人神戸いきいき勤労財団が運営している「ハッピーパック」に兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会として登録しようと考えております。本会が登録することで、上記同様の広告宣伝を行うことができ、ハッピーパックに登録されている神戸市内の企業(加入員数約4万4千人)の目に触れる機会が増え、健康経営に関する事業に繋がる可能性があると思われますので、是非、この事業にご参加ください。
参加をお考えの会員は県師会事務局へ登録をお願い致します。
なお、前回登録された方につきましても、意思の再確認をしたいと思いますので、再度登録をお願いいたします。
登録されました会員へは、後日、説明会についてご案内いたします。
【地区だより】
《たるみ生き活き保健福祉フェア報告》
報告者 神戸鍼灸マッサージ師会 副会長・学術部長 井上和哉
令和6年10月4日(金)9:30より垂水区社会福祉協議会主催の「たるみ生き活き保健福祉フェア」の一環として「はり・マッサージ体験施術」を行った。今年度からは神戸地区と垂水地区が合併したことにより神戸鍼灸マッサージ師会としての体験施術実施となった。
施術者14名(はり担当5名、マッサージ担当9名、ベッド8台(はり3台、マッサージ5台)体制で実施し、受療者数は48名(はり18名、マッサージ30名)だった。当日のキャンセルや当日申し込み等があり結果的には当所予定受療者数の体験人数となった。
私は鍼施術を担当し、6名の施術を行った(1名あたり約30分)。受療者は40代1名、50代1名、60歳以上4名とかなり高齢者層に偏った形だった。事前予約により施術枠がほぼ埋まっていたこともあり会場は盛況だった。施術させていただいた方にお聞きすると、半数以上の方が鍼施術は初めてということだった。その他の方は転居してきて鍼灸院を探しているがどこへ行けばいいかわからないという方もあった。1人あたりの施術時間は30分となっていたが、初診の上、施術後のフォローができないこともあり、効果を実感できる程度の刺激量とし、身体の動きの変化が感じられるよう動作のビフォーアフターを感じていただけるように施術を行なった。
今回、この保健福祉フェアでの体験施術にはじめて参加し、後ほど行なった垂水区社会福祉協議会の方との次年度に向けてのミーティングにも出席し、様々な検討課題があるように感じた。コロナ禍を経て、5年ぶりに再開した体験施術であったが、施術体験希望者への告知、募集方法、施術枠の設定方法や当日の運営に至るまで再検討が必要ではないかと思う。
このような各種のイベントでの体験施術やスポーツイベントにおける医療ケアの一端としてのボランティア施術は鍼灸マッサージ施術の啓蒙普及にも寄与することを期待し、できる限り参加したいと思う。また、体験施術等でご縁をいただいた方がその場だけでなく、どこかの施術院で継続して受療していただけるよう仕組みを考えたいと思う。
《西宮市民まつり報告》
西宮 瀧川敦子
西宮鍼灸マッサージ師会では、毎年市役所前広場で開催される西宮市民まつりへ出店しています。以前は、市民の方に無料マッサージ体験をしてもらっていましたが、スタッフ不足と費用対効果の関係で、一昨年から配布物(啓蒙チラシ、会員の施術所リスト、ツボのイラストチラシ、せんねん灸とコリスポットの試供品)のみにしていました。
今年は市民の方一人ひとりに接客をして、主訴を聞き、お灸かコリスポットを選んで体験をしてもらいました。
お灸は初めてで怖いけどやってみたいとの声が多く、65人にせんねん灸の体験をしてもらいました。ほんわりと心地よかった。家でも是非やってみたいがどこで買えるのか?昔やっていて押し入れの奥にしまっているが、出してまたやろうと思う。などの声が聞こえました。
スタッフは6名でしたが、来場者が途切れることなく接客に追われました。今年もせんねん灸とセイリンから試供品を提供してもらい、啓蒙チラシとともにお渡しし、喜んでいただけました。
セルフケア用のテニスボールマッサージ用のボールは例年とても人気で、2個連結50個と1個を150個用意し、使い方のチラシとともにご自由にお持ち帰りくださいとしたところ、またたく間になくなりました。
来年は西宮鍼灸師会と合同で出店できるよう調整していきたいと思っています。
開催日:令和6年10月26日(土)11時~16時
会員スタッフ:6名
お灸体験:65名
凝りスポット体験:45名
《西宮市研修会報告》
報告者 杉輝章
11月17日(日曜日) 西宮市関西盲人ホーム昭和寮に於いて、西宮鍼灸マッサージ師会の研修会が開催されました。
加古郡稲美町はりきゅう尚庵の山口尚代先生を講師にお招きして、テーマは「お灸療法〜知熱灸を取り入れよう!」です。西宮市だけでなく市外からの先生も含めて15人の参加でした。
最近お灸の良さが見直され夏期大学でも取り上げられてはおりますが、使われるお灸はほとんどがセンネン灸などの台座灸です。モグサを指先で捻って直接体に据える透熱灸や知熱灸は、開業鍼灸師の間でもあまり使われておらず、聞いたことはあるけど見たことはない、とか知っているけれど使ったことがない、と言った先生方がほとんどなのが現状だと思います。
山口先生は大阪の松浦鍼灸大学堂で5年間、お灸を中心とした鍼灸臨床の修行をされ、その後ご自身の鍼灸院でもお灸を活かした施術をされています。
前半はパワーポイントを使って、お灸についての説明や臨床においての使い方、よく使うツボの解説などをしていただき、後半は普段使っているお灸のセットを使っての実技をしていただきました。模擬患者役をされた先生は知熱灸を受けたことがない方で、山口先生のお灸を体験して「これが本当のお灸なんですね!」と驚かれた様子でした。
山口先生の知熱灸は、半米粒〜米粒大のモグサを据えて線香で火をつけ、それが八分くらい燃えたところでその上に次のモグサを重ねるというやり方で、これを5壮から10壮くらいまで繰り返します。1壮ずつ消すやり方に比べはるかにスピーディーで、手際の良い施術でした。
実際に寝違えて首が痛いという人(中南会長)に、この知熱灸をすると首の痛みが軽減して可動域が広がったというのも目の当たりにすることができました。
最後は分かれてお互いに練習をしましたが、当然のことながら上手く出来ず、山口先生の技術の高さを認識いたしました。
その翌日から私の鍼灸院でも(山口式の)知熱灸を取り入れています。初めのうちは手際が悪く何人かの患者さんに熱い思いをさせてしまいましたが、施術後に肩や腰が軽くなったと言った反応がありましたので、これは効果があるなと実感しているところです。
鍼灸院という看板を掲げているにもかかわらず、お灸はあまりしていない先生がほとんどだと思います。お灸はとても効果があるだけでなく、お灸を据える時間が患者さんとのコミュニケーションになることや、お灸の香りや煙が漂っている雰囲気が癒しの空間を作ります。
山口先生のお灸愛に触れて、私もそのスタンスがとてもいいなと思いました。私の鍼灸院もお灸の香りが漂う憩いの場にしたいと思います。
お忙しい中にもかかわらず資料を準備してご講演いただいた山口先生ありがとうございました。またご参加の先生方お疲れ様でした。
これからも鍼灸マッサージを盛り上げて行きましょう!
《姫路ブロック臨床研修会報告》
報告者:佐藤暢彦
11月17日(日)午前10時より姫路市民会館5階第1教室にて、宝塚医療大学講師の岡田岬先生にお越しいただき『消化器疾患と自律神経の関係 -鍼灸治療のメカニズム-』を講演していただきました。
岡田先生は鍼灸師の免許を取り、臨床現場を経て研究の道に進まれた方です。鍼灸がどのように身体に影響をもたらしているのか興味を持たれ、ラットを用いて鍼灸のエビデンスを大学で研究をされています。
■消化器と自律神経
神経系の基本では中枢神経系(脳・脊髄)と末梢神経系(体性神経系・自律神経系)の大きく二つに分かれる。そして末梢神経系は体性神経系と自律神経系に二分される。その自律神経系もまた求心性(内臓求心性神経)と遠心性(交感神経・副交感神経)に二分される。
内臓求心性神経は内臓感覚を脳や脊髄へ伝える神経であり、交感神経や副交感神経と同じ神経束内を並走する。内臓感覚は臓器感覚と内臓痛覚に分かれる。臓器感覚(空腹、口渇、便意、尿意)は主に迷走神経・骨盤神経といった副交感神経を通る。内臓痛覚は主に交感神経を通る。
消化管に分布する自律神経のうち、交感神経は『闘争または逃走』の機能を有し内臓の消化機能を抑制し骨格筋にエネルギーを送る。一方の副交感神経は『休息と消化』の機能を有し消化機能を昂進させる。
特に内臓求心性神経は迷走神経を通っていることもあり、耳の穴付近(迷走神経が分布する)の刺激が効果的である。例えば、耳を温めることや、テイ鍼などの柔らかい刺激をすることで、自律神経を安定させ、内蔵を安定させる効果が期待できる。
■消化器に対する鍼のメカニズム
鍼刺激は胃運動にどのような影響を与えるのか?
手、足などの末端部からの刺激は副交感神経を使っており、胃の運動を促進させる。逆に体幹からの刺激は交感神経を使っているために胃の運動は抑制される。
具体的には『曲池や足三里』などの手足末端のツボ刺激は胃運動を促進させ、『膈兪、肝兪、脾兪』のいわゆる胃の六つ灸は体幹のツボ刺激であり胃の運動を抑制させる。よって、消化不良などの胃の動きが悪い時には曲池や足三里を使うことが効果的であり、逆に胃痛などの過剰な刺激を落ち着かせる時は胃の六つ灸を使うのが効果的となる。
胃痛時に胃の六つ灸を使うのが効果的と述べたが、大学での授業時に「何故、胃の六つ灸に胃兪が入っていないのか?」という質問を学生から受けたことがある。これに関して体のデルマトームを参照にすると、Th12(胃兪)の神経支配は胃の辺りを支配をしていないことが関係していると思われる。
【加古川ツーデーマーチ報告】
報告者:賀内淳一郎
11月9日(土)、10日(日)の2日間、加古川市役所を中心とした加古川市内にて、「第34回加古川ツーデーマーチ」が開催された。距離は20km、10km、5kmの3種の設定がされ、年代問わず参加がしやすい様設定がされていた。コースの各所に設置されたチェックポイントでも様々なイベントが開催され、会場全体としてゆったりと楽しんでいる空気が流れていた。事前の予報では荒天の可能性が示されていたが、2日間共に快晴で、穏やかな日差しの中での開催だった。
今回は、スポーツマッサージに加えて、鍼での施術も参加者が選択できる準備をしていた。また、家庭でのケアのための試供品も提供いただいていたため、施術を受けた方々には施術後に渡していた。
1日目は、ゴール後のウォーカーに対する施術が中心で、昼頃から終了時刻である16時頃まで、約80名の方が施術を受けた。運動直後なのもあってか、スポーツマッサージの希望者が圧倒的に多かった。また、過去の開催時に参加していたウォーカーのリピートも多く見られた。2日目になると、まずは両日参加のウォーカーの出発前の施術希望が増えた。中には10歳以下の児童も含まれ、身体のケアの重要性がより幅広い世代に認識されつつあるのではないか、と感じさせた。また、一日目に比べると鍼での施術を希望するウォーカーが圧倒的に増えた。1日目の疲労が残った状態で2日目に参加したウォーカーが多かったようで、連日の施術希望も多数見られた。鍼希望者の多くが、鍼での治療を受けるのは初めてだったようだが、受けた人の多くが身体が軽くなったことを実感し、とても喜んでいただけたようだった。施術中に「〇〇市で鍼灸をやっている治療院はあるの?」といった質問が出ているのも散見した。一度治療を受けたことで、ウォーカーの中で鍼灸が治療の選択肢に含まれるようになっていっているのではないか、と感じられ、とても充実したイベントだった。
=会員情報=
7月21日からの入会者 0名
7月21日からの退会者 5名
11月15日現在会員数 229名
【事務局からのお知らせ】
<年末年始休業のお知らせ>
恒例のことですが、当事務局は下記の通り年末年始を休業させていただきます。何かとご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。
休業日:12月28日(土)~1月5(日)
◇◇編集後記◇◇
今号も前号に続き芋料理になってしまいましたがご容赦ください。
冬の美味しい食材の一つに「さつまいも」がありますよね。いくら美味しいからと言っても焼き芋ばかりじゃ飽きてしまいますし、スイートポテトを作るのもめんどくさいですよね。前述した食べ方はいずれもオヤツですが、おかずや酒のあてになる一品をご紹介します。極々簡単ですので作ってみてください。
《さつまいも煮》
‘材料’
・さつまいも・・・1本(約300g)
・めんつゆ・・・・100ml
・水・・・・・・・400ml
※めんつゆは4倍濃縮を使っているので水との割合が1対4です。3倍濃縮なら1対3
‘作り方’
1.さつまいもを亀の子たわしでしっかり洗い3cm幅にカット。
2.鍋にめんつゆと水とカットしたさつまいもを入れる。
注:いもがしっかり浸かっている事。
3.アルミホイル等で落とし蓋をし中火にかける。
4.沸騰したら弱火にし、12分たったら火を止める。
5.常温になるまで放置したらできあがり。
♪器に移してお召し上がりください。♫
広報部長 天野 豊
【発行所】 公益社団法人 兵庫県鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会
〒673-0018 明石市西明石北町3丁目8番15号
TEL (078)-926-0801 FAX (078)-926-0802
mail info@mam-hyogo.or.jp
【発行者】会長 賀内進一 【編集担当者】広報部長 天野 豊