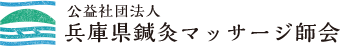2025/03/27
《神戸ブロック臨床研修会》
令和7年1月26日(日) 13時30分より鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部鍼灸サイエンス学科 准教授 本田達朗 先生をお招きし、「【M-Test】の理論と臨床実践テクニック(初級)」との演題で講義と実技指導を行なっていただきました。今回は会場とオンラインのハイブリッド開催とし、体調不良等による欠席者もありましたが、会場14名、オンライン6名の合計20名が受講しました。
【M-Test】は「痛み」「突っ張り感」「重さ」「だるさ」といった身体に感じる異常所見や違和感を誘発する動作から、アプローチする面(経絡や筋)や点(経穴)を特定し、それらの経絡経穴や同一面上にある硬結等の異常所見を正常な状態へ改善することで身体の動作やバランスを整える療法です。そして、身体動作と経絡をどのように結びつけていくのか?ということですが、これには手足の三陰三陽経の経絡流注を知っておく必要があります。経絡図に描かれている姿位、いわゆる「気をつけ」の姿勢が基本姿勢で、手足それぞれの三陰三陽経を前面、側面、後面に分類します。上肢であれば前面は肺経と大腸経。側面は心包経と三焦経。後面は心経と小腸経となり、下肢では前面は脾経と胃経。側面は肝経と胆経。後面は腎経と膀胱経といった分類となります。大腿部では腎経は内側前方へ流注しますが、ここでは後面に分類されます。
そして、【M-Test】では簡単な33種類の動作から、動きの悪い動作をチェックしていきます。そして、その動きが悪くなっている動作を行う時に伸びにくくなっている面・経絡がどこかというように特定していきます。例えば上肢の前方挙上、つまり肩関節屈曲動作が行いにくい場合は伸展される後面の少陰心経と太陽小腸経が施術対象経絡という具合です。施術対象経絡の選定ができたら、次はその経絡中の経穴に施術していきます。【M-Test】では基本になる経穴は手足の三陰三陽経にそれぞれ2穴あり合計で24穴が基本穴になります。この24穴はいずれも五兪穴で、それぞれの経絡上の2穴は対象経絡五行分類と同一穴を自経穴、その経穴の母穴と子穴を対象経穴とします。例えば、手の太陰肺経であれば五行では金に属しますから自経穴は経金穴の経渠、母穴は兪土穴の太淵、子穴は合水穴の尺沢になります。陽経は五行配当がズレますので、同じく五行の金に属する陽明大腸経では自性穴は井金穴の商陽、母穴は合土穴の曲池、子穴は栄水穴の二間となります。これらの経穴に毫鍼や円皮鍼や灸、あん摩・マッサージ・指圧師の有資格者であれば指圧などを行い、スムーズな動きができるよう施術していきます。本田先生はあん摩・マッサージ・指圧師の免許もお持ちということで、刺激の仕方は特定の刺激に固執せずに複合的に行なった方がよいとお話されていました。スポーツ選手と関わることが多かった経験からそのような考えに達したともお話されていました。また、アプローチする経絡が特定できれば経穴のみだけでなく、その経絡上の筋肉所見にたいしてもアプローチすることは有効であるともお話されていました。
今回は初級講座ということで【M-Test】の基本的な部分をお話と実技指導していただきました。基本的なアプローチで症状が軽減しない場合はさらに施術対象の経絡や経穴の運用方法の応用があるとのことです。そのあたりの内容は中級・上級講座でご指導いただけるとのことですので、会員の皆様のご希望があれば中級・上級講座の企画をしたいと思います。
あと、研修会の終盤に本田先生がお話された内容で印象に深く残っていることがあります。それは本田先生が大学の臨床に来られていた患者さんで治療経過がよろしくない方があり、セカンドオピニオンを進めた結果、大学病院でALSの診断を受けた患者さんがあったとのお話でした。その患者さんは以前から整形外科にはかかっていたそうですが、通院していた「整形外科の先生に悪いから」と言って当初はセカンドオピニオンを渋っておられたそうです。それで、本田先生が「セカンドオピニオンは悪いことではないから」と説得して、三重大学病院を受診し上記の診断となったということでした。施術者・治療家は自身の技術を磨き、その技術に自信を持って患者さんを診察すべきだと思いますが、その技術に固執したり慢心し、視野が狭くならないように肝に銘じて日々の臨床に当たりたいと思います。
【報告者 神戸地区:井上和哉】